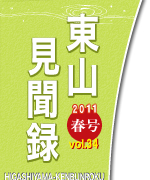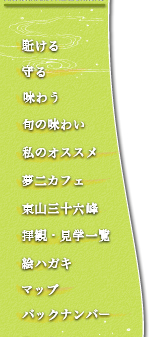|

〜大きな葛篭と小さな葛篭、どちらか好きな方をお持ちくださいな。
『舌切り雀』でおなじみの葛篭は、古くから日本で親しまれてきた入れ物。今も昔と変わらぬ手仕事で作り続けている京葛篭師、渡邉豪和さんのもとを訪ねました。
ピシッ、ピシッー。路地に響くのは、竹を割る小気味よい音。ここ渡邉商店は、籠作りから和紙張り、塗り、仕上げに至る葛篭作りの全行程を一貫してこなす日本でただ一軒の工房です。
 「親父がこの仕事を始めた頃、うちは竹籠を作る下生地師だったんです。私も物心ついた頃から竹を剥ぐ稽古をして、中学の頃から親父の手伝いをしていましたね」。当時の葛篭作りは、和紙を貼る「張り師」、漆や柿渋を塗る「塗り師」など、行程ごとに分かれていましたが、時代の流れとともに需要が減り、職人の数も減少。そんな状況の中で渡邉さんは、すべての行程を自分で手掛けたいと思うようになったのだそうです。 「親父がこの仕事を始めた頃、うちは竹籠を作る下生地師だったんです。私も物心ついた頃から竹を剥ぐ稽古をして、中学の頃から親父の手伝いをしていましたね」。当時の葛篭作りは、和紙を貼る「張り師」、漆や柿渋を塗る「塗り師」など、行程ごとに分かれていましたが、時代の流れとともに需要が減り、職人の数も減少。そんな状況の中で渡邉さんは、すべての行程を自分で手掛けたいと思うようになったのだそうです。
「竹選びから仕上げ、お客さんに届けるところまで一貫してやるのが、本来の職人の姿なんじゃないかと思ってね、全部自分でやることにしたんです」。
渡邉商店の葛篭に使われるのは、長岡京産の4年ものの孟宗竹。一昼夜水に浸けてから割り、使い込まれた刀で1ミリ以下の薄さに剥いでいきます。剥いだ竹は炙って籠に編み、和紙を貼る。さらに補強のための蚊帳を貼って、松煙や紅殻で下地を施し、色を塗り重ねる。実に手間を惜しまず25の行程を経て完成する京葛篭は、まさに用の美を極めた美しさ。
「いろんなご縁に恵まれたおかげで、私は本当にいい仕事をさせてもらってきました。大相撲の明荷(あけに)や歌舞伎の装束入れ、東大寺お水取りで練行衆(れんぎょうしゅう)の方がお持ちになる大葛篭。”本物”を作れば、胸を張ってどこへでも出せる。そういう意味で、職人としての自分の夢は叶っているのかも知れませんね」。
その手技のすべては長男の良和さんに受け継がれています。
|
|

その見かけから、関西で“ぼて”と呼ばれる葛篭。耐久性に優れ、補修すれば100年は持つと言われる通り
「私が戦後父のもとで仕事するようになりはじめた頃のもんが今も修理で回ってくる」とのこと。 |